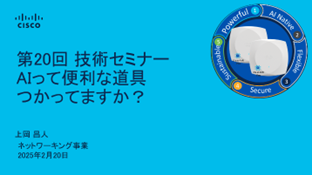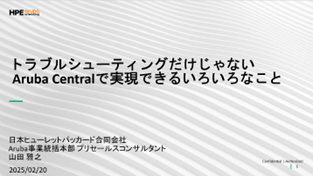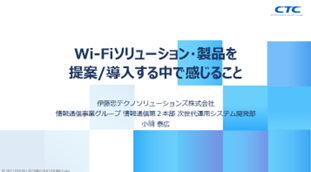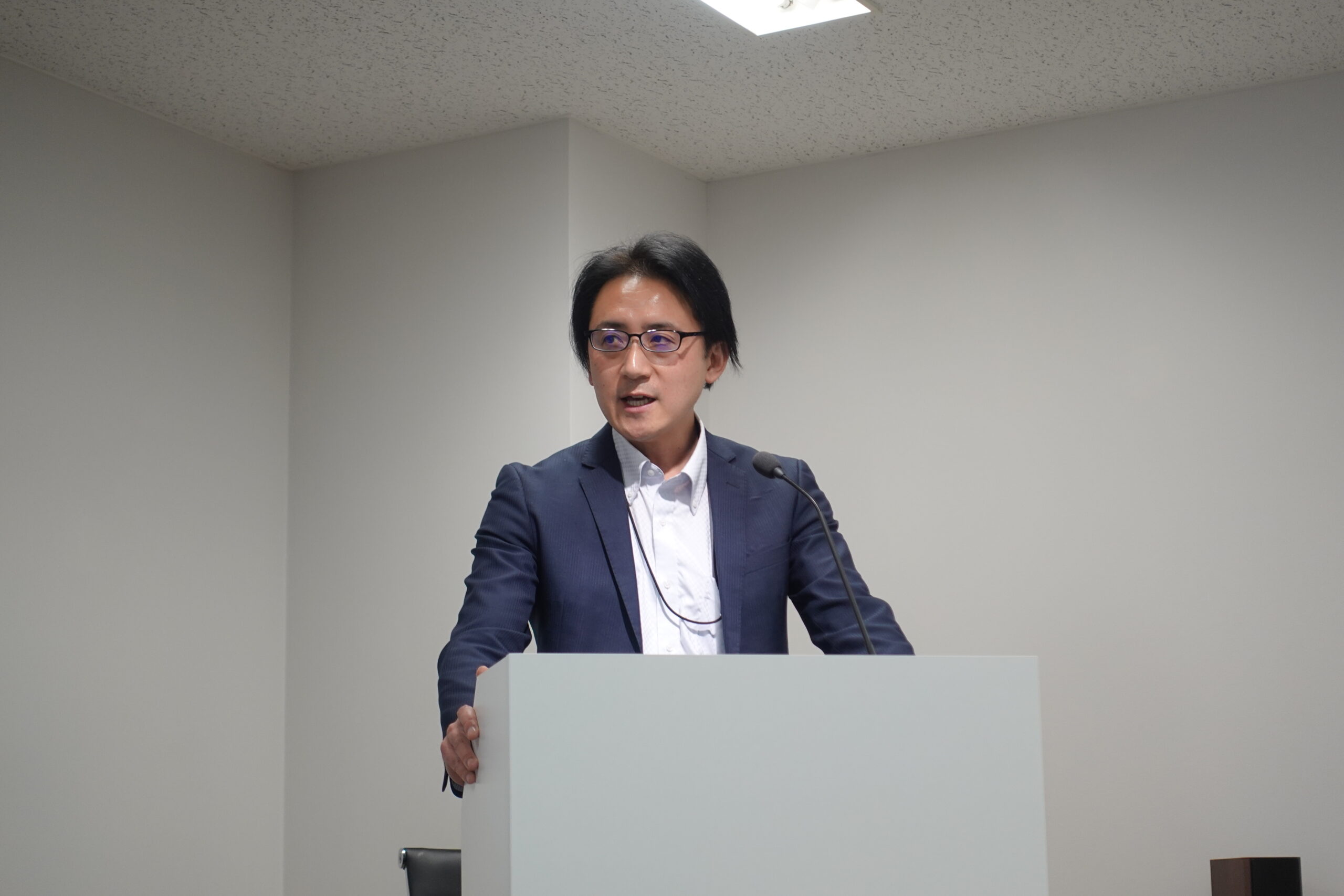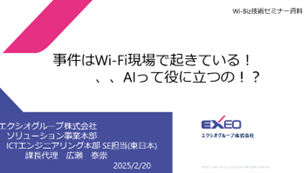毎月の記事やお知らせをぜひお見逃しなく!
メールマガジン配信登録は☆こちらから☆
活動報告
第20回技術セミナー
好評の「Wi-Fiトラブルシューティング2025」を開催
技術・調査委員会 本橋 篤
2月20日、技術セミナーのアンケートでも常に関心の高いトラブルシューティングをテーマに、第20回技術セミナー「Wi-Fiトラブルシューティング2025 -あなたに代わってトラブル解決-」を株式会社ビーマップの会議室をお借りしオンラインにて開催しました。トラブルシューティングは3年前の2022年3月の第16回技術セミナーでも取り上げていますが、今回は、データ活用やAIによる分析といった新たな技術とその導入にフォーカスし、メーカーおよびシステムインテグレーターのそれぞれの立場で4名の方に講演いただきました。
会長挨拶
冒頭、北條 博史会長から挨拶があり、Wi-Fiは免許不要で誰でもAPを置けるのがメリットである。正しく使えば便利に使えるが、電波は目に見えないこともあり置き場所に起因するトラブルや通信干渉のトラブルがあった事例が紹介されました。
今回は20回目のキリの良い技術セミナーで200名近くの方が申し込んでいると報告され、疑問点はQA機能を活用しセミナーを楽しんで頂きたいと参加者に呼びかけました。
AIって便利な道具つかってますか?
|
|
最初の講演は、シスコシステムズ合同会社の上岡 昌人様から、シスコ社のAI機能の取り組みについて説明がありました。
冒頭、発表されたばかりのiPhone 16eでもAIが使えるようになったことに触れられ、どこでもAIが使えるようになってきているのでWI-Fiの領域でもこの流れを進めていきたい。AIは万能ではなく、いかに使いこなせるかが重要であると述べました。
シスコのAIアシスタントにより、会話形式でプラットフォーム全体のインサイトを提供することや、目に見えていない電波や認証やアドレス取得の失敗などのWi-Fiのオンボーディング分析、クライアントからのデータも分析に用いることで、使い心地の可視化や改善が可能なことが示されました。
最後に、無線状況や近隣 AP の情報、端末の情報を学習することで、自動調整と可視化を行い無線電波環境を改善した事例や、MLOなどWi-Fi 7 の新機能のAIによる活用が示され講演を終えました。
トラブルシューティングだけではない
Aruba CentralのAIで実現できるいろいろなこと
|
|
続いて、日本ヒューレット・パッカード合同会社の山田 雅之様からArubaのAIの取り組みについての講演がありました。
冒頭Aruba Centralは日本ではAWS東京リージョンを2014年から利用しており、10年分の情報が溜まっていることが紹介され、サードパーティのIT機器をクラウドで統合管理することにより他社混在環境でもAI分析が可能であることや、クライアントにとって最適なAPに接続を促す機能、周辺APの電波の重複具合や利用者数を監視し機器のファームのバージョンアップを日中でも可能にする機能、推奨される設定変更を自動で反映する機能、不具合の種類を判断してログ・キャプチャを自動的に採取する機能などが示されました。
最後に次世代のAruba Centralの概要が紹介され、新しいユーザーインタフェースをぜひ使ってみて欲しいとして講演を締めくくりました。
Wi-Fiソリューション・製品を提案/導入する中で感じること
|
|
次は、システムインテグレーターの立場から、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の小關 泰広様が講演を行いました。
Wi-Fiのお客様は、接続性・安全性・性能・運用などきちんとつながることを求めており、期待値を下回るとトラブルになること、水道・電気のようにインフラと思われるがトラブルは水道や電気よりも多いと説明されました。
企業のお客様への提案では、天井設置のためにサイズ・重量を気にするお客が多いこと、全世界や国内での導入事例を気にするお客様も多いこと、5年間のランニング費用を含めたトータルコストが関心事であることなどが示されました。
最後に、Wi-Fiはつながることは当たり前になったため+αの付加価値やメリットを提案する必要があり、Wi-Fiを構築することはコストであるという考え方からWi-Fiにエンドユーザーがお金を使いたくなる仕組み(マネタイズ)に発想を転換することが必要であるとして、講演を終えました。
事件はWi-Fi現場で起きている!、、AIって役に立つの!?
|
|
|
最後の講演として、エクシオグループ株式会社の広瀬 泰崇様から、様々なWi-Fiトラブルシューティングの事例が紹介されました。
遅い・つながらないがWi-Fiトラブルの2大キーワードであり、Wi-Fi更改前後におけるトラブルシューティング手法としてダッシュボード機能の活用をあげつつも、無線キャプチャを実施し解析するという人力や足を使った手作業での調査が主力であることが示されました。
続いて、ホテルの客室Wi-Fiのスループット低下の事例、角部屋や天井裏における電波到達の問題、マルチキャストのmDNS通信問題事例、有用なトラブル解析ツールが紹介されました。
最後に、ユースケースやスキルを持ったエンジニアのナレッジの肩代わりがAIへの期待だとして講演を終えました。
セッションQA
最後のコーナーとして、技術・調査委員会 本橋 篤が司会を担当し、Q&Aセッションを実施しました。
質問: メーカーを跨いで機器の情報をAIが把握するために標準化の動きはありますか?
回答1: IETFのような標準化に期待したい。Syslog、SNMPなど既存のプロトコルをベースに実装するのがよい。機器固有の機能の標準化には時間がかかる。
回答2: 機能としてSNMP、Syslogに加え、APIを利用している。今のところ標準化の動きは聞こえてこない。AIを使用したネットワーク管理はこれから広がっていくのでは。
質問: もっと使って欲しい便利な機能はありますか?
回答: RMM(無線リソース管理)を使って欲しい。RMMなくしてWi-Fiの安定はない。シミュレーションでもトラブル抑止に有効。
質問: APの配置の工夫だけでは、端末が最適なAPに繋がってくれないと思いますが、ローミングの最適化はどのくらい有効なのでしょうか?
回答: 移動を促すためにAPから切断が必要なため、APの密度によっても動作が異なる。うまく動かなかったらサポートに連絡を。APの入れ替えだけでなく、ローミングの新しい規格に対応した新しい端末に入れ替えも有効。
質問: 日中でもAPのバージョンアップが可能ということですが、使いたいですか?不安点ありますか?
回答1: 自動になるのはありがたい。利用者のトラフィックが全くなければ、利用したい。
回答2: Wi-Fi利用者が自己責任でやるならよい。日中の方がトラブルシュートが手厚くできる。夜間に体制を作ってできるのが一番。
質問: AIによる品質の向上、運用の効率化について、コスト削減ではなく価値向上としてお客様にとって認知してもらうに必要なことは何でしょうか?
回答1: エンジニア・運用者観点だと、AIでトラブルシュートできるのは価値があるが、コスト削減だけでは弱い。明らかなUX向上などがあればよい。
回答2: AI切り分けの話はお客様の食いつきが良いが、導入になるとトーンダウンする。お客様から見て、ベンダの人力で対応するのと機器のAIで対応するのどちらが良いか?という話になる。
Wi-Fiに価値を感じてもらいマネタイズするには?これからのWi-Fiはどうなるか?
小松 直人委員長から、技術セミナーの締めのご挨拶にかえて以下のコメントがありました。
以前見たアメリカのスタジアムのWi-Fi・ネットワークの設備がデータセンターのようになっており、そこでの投資はWi-Fiを提供するだけではなく、プレビューの動画コンテンツ配信やスタジアム側がTV局に映像を提供するなどのマネタイズのモデルが存在していた。Wi-Fi接続の提供だけでなく、コンテンツを使ってもらうためのトータルなネットワークインフラとしてマネタイズされている。AI活用によって、これまでと違うことに時間や能力を使えるようになるとよい。
■Wi-Biz通信(メールマガジン)の登録はこちら